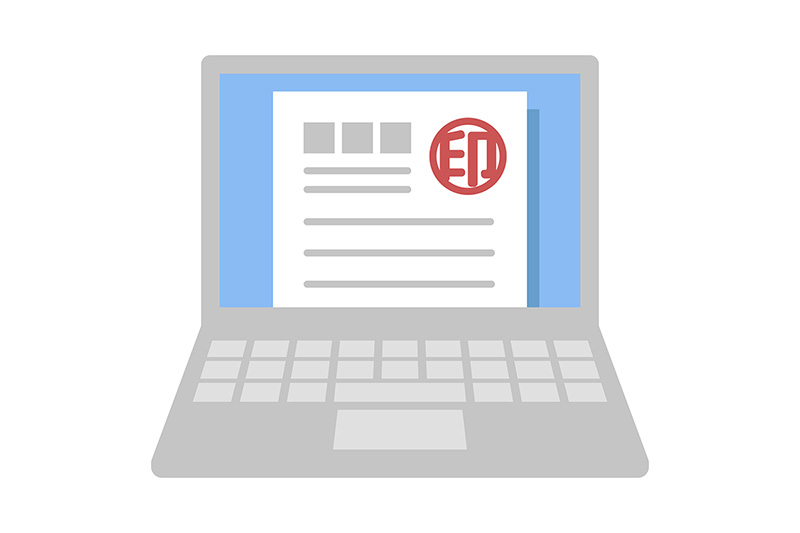
事務処理に用いる書類のペーパーレス化を進める際、避けて通れないのが法制度の問題です。管理業務で用いる書類には、電子化・ペーパーレス化の可否を定める2つの代表的な法令があります。「e-文書法」と「電子帳簿保存法」です。
今回は電子文書と電子“化”文書という2つの用語の違いを整理しつつ、少し複雑な法律を読み解くための基本的な考え方を解説します。
一見すると電子文書と電子化文書は同じように見えますが、実はまったく意味が異なります。
法律の違いを確認する前に、まずは電子文書と電子化文書の違いを押さえましょう。
電子文書は、最初からすべての情報がデジタルデータで作られた文書を指します。
例えばWordなどのような文書作成アプリケーションを使って作成し、保存した文書ファイルが該当します。
一方、電子化文書は、最初は紙文書だったものを後から電子“化“したものを言います。
わかりやすい例としては、初めは紙媒体にプリントアウトされていた書類を、スキャンを取ってPDFファイルにしたような場合が当てはまります。
ここでは e-文書法と電子帳簿保存法の概要についてご説明します。
「e-文書法」は通称で、2つの法律の総称として使われています。なお、「電子文書法」と呼ばれることもあります。正確には「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、これら2つの法律から成り立っています。 e-文書法の制定によって、書類の保存規定および保存義務について定めた約250本の法律を改正することなく、書類の電子保存が可能になりました。
「電子帳簿保存法」は通称で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。この法律により、国税関係帳簿書類を電子データで保存する方法は、次の3種類になりました。
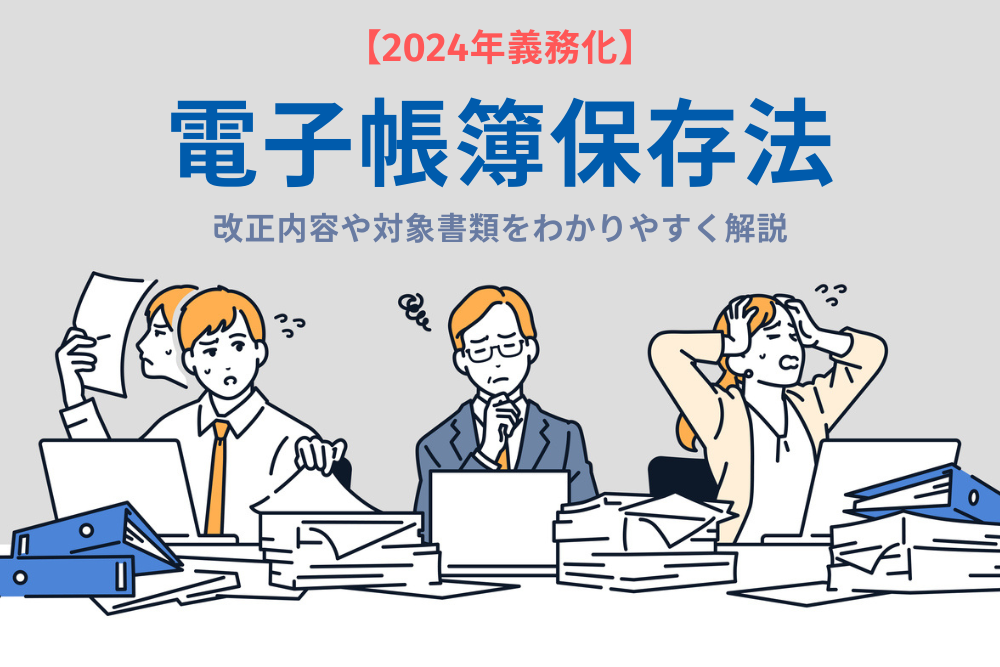
電磁的記録による保存:各種書類をPCで作成し、印刷せずサーバやDVD、CDなどに保存する方法。
COM(電子計算機出力マイクロフィルム)による保存:各種書類をPCで作成し、COM(電子計算機出力マイクロフィルム)によって保存する方法。
スキャナによる保存:紙の書類をスキャンしてデータに変換して保存する方法。なお、スキャナ保存の要件が2016年の法改正により緩和され、デジタルカメラやスマートフォンのカメラでも保存可能になりました。
どちらの法律も、こうした電子文書や電子化文書としての保管の可否を定める法律です。
以下では、それぞれの法律の対象となる文書について解説します。
民間事業者等において、法人税法や商法などの法律により保管する義務がある書類が多数存在しています。e-文書法は、その保管義務がある文書の電子データ保存を容認する法律です。
帳簿、領収書、請求書、納品書、預金通帳、建築図面、診察記録などが対象となっています。なお、保存可能な文書の詳細は内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室の「e-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定」で確認ができます。
【参考】内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
「e-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定」
電子帳簿保存法は、主に国税に関する書類を電子データで保存することを認めた法律です。
もともと電子帳簿保存法は、e-文書法が制定される前から存在する法律でしたが、e-文書法が制定されたタイミングにあわせて改正され、書類の電子化の要件を定める法律となりました。
書類を電子化するメリットとしては、原本の保存が不要になること、コストの削減、業務の効率化という、大きく分けると3つのポイントがあります。
これは、保存義務のある書類について、紙として原本での保存が不要になるものが多くなったためです。原本での保存が不要の場合、電子保存ができていれば良いとされています。
電子保存だけで良い場合、従来必要であった書類の保管場所の確保や、紙の書類を郵送するコストが削減できます。さらに、データを印刷せずに済むため、紙代や印刷代などのコストも削減ができます。
電子保存したデータは、紙の書類に比べて検索が容易であり必要な書類を取り出しやすいため、業務効率が向上しやすいというメリットがあります。
なお、検索を容易にする方法として、タイトルの付け方や内容によってフォルダの分け方も工夫すると良いでしょう。さらに、データをクラウド上に保存しておけば社外からでも内容を閲覧・確認できるようになり、テレワークで働く社員にとっても便利でしょう。
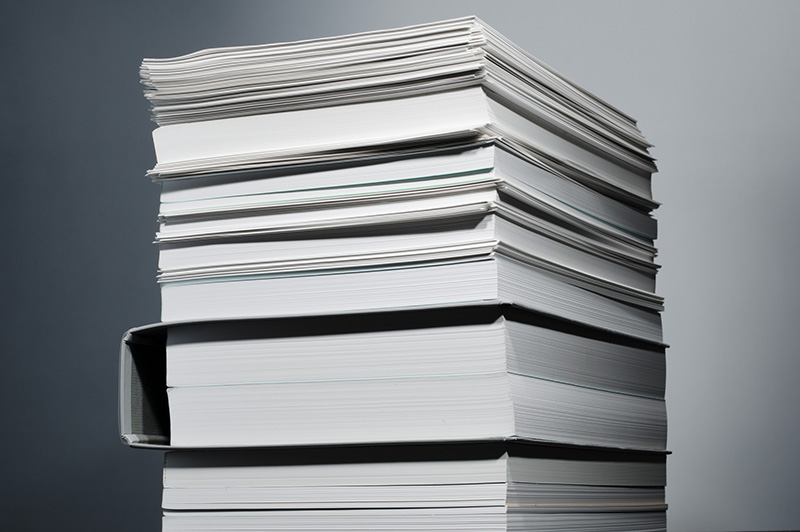
ここまで書類を電子化する際のメリットを説明してきましたが、電子化にはいくつか注意が必要なポイントがありますので確認しておきましょう。
e-文書法と電子帳簿保存法ではすべての書類の電子保存が認められているわけではないため、紙書類の原本の処分は電子保存が可能なことを確認してから行いましょう。
電子保存が認められていない書類の主な例としては、手書きで作成した仕訳帳、手書きで作成した請求書の写しなどがあります。
では、電子保存の際の必要条件を確認しましょう。
e-文書法では、4つの技術的要件が定められています。
続いて、電子帳簿保存法では真実性と可視性の要件を満たすことが求められています。
デジタルデータは紙文書と比較して複製が容易で改ざんされやすいため、タイムスタンプや電子署名を併用するようにしましょう。タイムスタンプは、時刻配信局などの第三者機関を利用することで時刻情報の改ざんを防ぎ、日時の真実性を担保してくれる仕組みです。
実際に、電子帳簿保存法ではタイムスタンプの付与が義務付けられています。他方、電子署名は作成者を特定するために用いられます。電子帳簿保存法では電子署名の使用は必須ではなくなりましたが、訴訟対策や原本性の担保のため広く用いられています。
電子帳簿保存法の対象文書を電子保存する際には、税務署の許可が必要です。一方、e-文書法の場合は事前許可が不要です。電子保存にしたい文書がどちらの法律に関連しているか確認しましょう。
今回は、電子文書と電子化文書の違いから、 e-文書法と電子帳簿保存法というペーパーレス化にかかわる法律についてご説明しました。全体像を前もって頭に入れておくことで、情報収集や利用ツールの選定もしやすくなるでしょう。これらの法律を理解して電子保存を活用し、業務の効率化を目指しましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
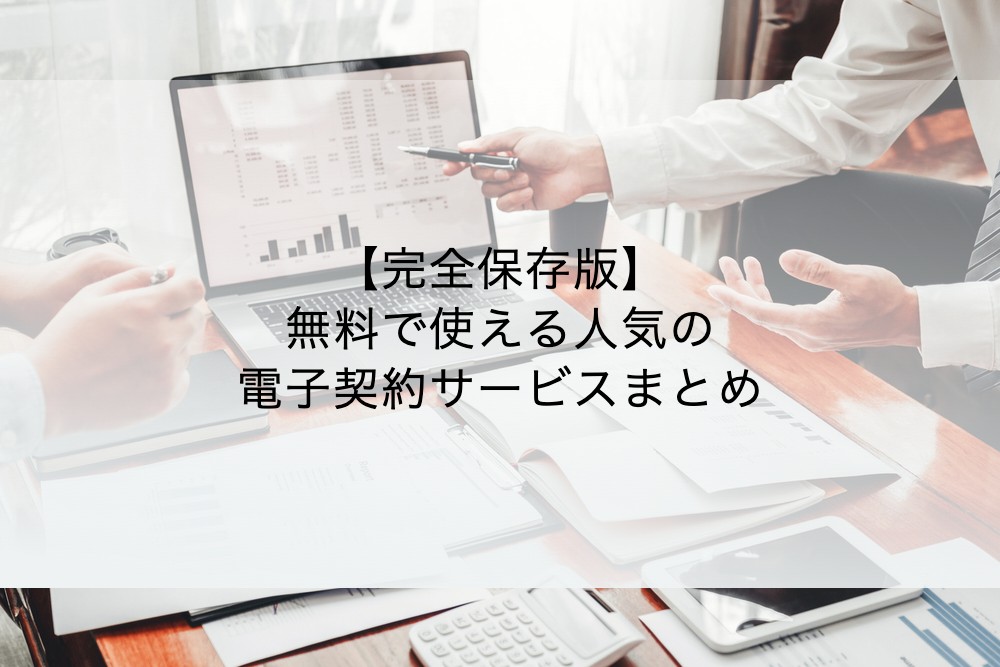
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、300万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。
